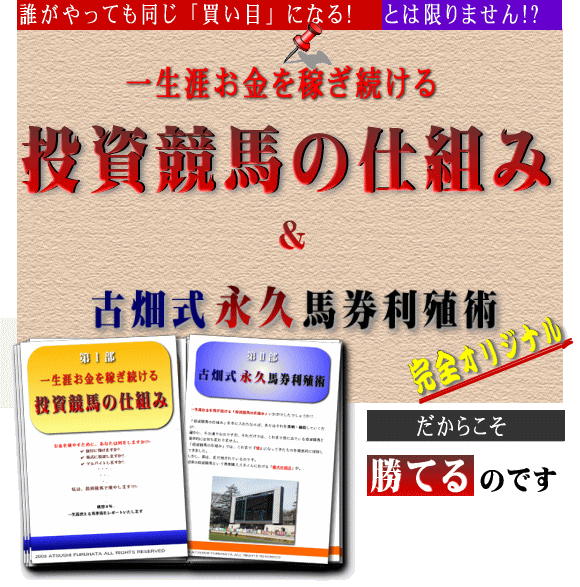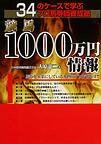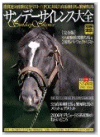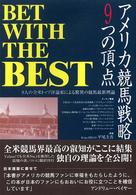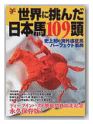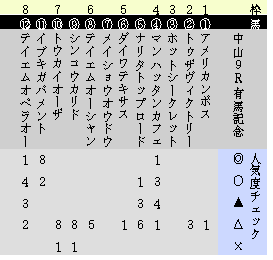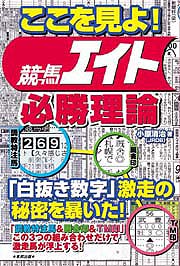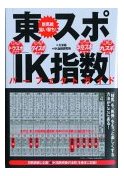| �n���{��� |
�n�}���x |
����x |
�|���I��\�n���{�|�@ |
|
|
|
|
| ��{�n |
������ |
�� |
�R�����g |
�@
�@�����n�V���̌�������N���X�ւ��A�x�����n�̎�̑I����R��̂��ƂȂNJ�{�I�Ȃ��Ɓi������Z�I���[�Ƃ�����j�������Ă��������܂����B
�g�[�^���ōl����A�n���̎�̑I���ɂ͎����Ȃ�̊�{�������A�������邱�Ƃ��厖�ɂȂ�Ǝv���܂��B�����͌����Ă��A����x�����P�Ȃ̂́A���̃X�^�C���ŏ��������邱�Ƃ�����Ǝv������ł��B�v���ł��鋣�n��厏�̋L�҂����̉����������A����͖��炩�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�@�@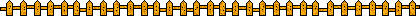
���������̍ŋ��̔n���p�i���������j�|������
��C�e�B���O�����j�A�����������������n���펯�{�B�h���n�̓L�`���Ƃ����Z�I���[�����Ɏ��g�݁A�}�W���ɋ��K�Ǘ����s���Ă����P�O��P�O���Ƃ܂ł͂����Ȃ��Ă��A�����X�p���ł݂�ΕK���ׂ���h�Ə�����Ă���B�͂����āA�ǂ����B���C�e�B���O�����قǔn�ɐ��ʂ��Ă��鎁�Ȃ�Ƃ������A���������T�����Q�T���̕ǂ�˂��j�邾���̃Z�I���[�����̂ɏo���邩�������ƂȂ�B
�����n�@�V�˂ɂȂ�q���g�|�����n���ŕ����Ȃ��U�T�̕��@�|�i���������j�A�[���Y�o����
�s�P�U�N�ԂłP�T��̍������x�Ƃ������҂��������B�����̔n���̔������ɔY���ɂ͂��̖{���ǂ����B�n���̃Z�I���[�ƌ������́A�n�����l�ԐS���Ƀ��X�����Ă���t
�����n�f�[�^���ꂪ�~���������@�����V���i��ˏG�����j�˓`����
�s���[�X�̊�{�f�[�^���ځA���Â��Ȃ������͂��邪�A�܂��܂��g����B����Ӗ��A���̃f�[�^�̐��X���Z�I���[�Ƃ������̂�������Ȃ��B�t
���ɉ��I�݂�݂铖����u�g�ݗ��Ď��v�\�z!!�i�ؓ��C�i���j���M�o�����@�s�{���͂O�P�N�W���ȍ~�ɏo���n���{�̒��ł͔��ɃI�[�\�h�b�N�X�ȃZ�I���[�n���{�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Z�I���[���P�P�g�ݗ��ĂĂ����Ƃ������z���V�����t
�����������l�A�����l�̋��n�V���̌����@���c ����Y (��)
�@���l�́A���n�V�����ǂ��ǂ݁A�ǂ��\�z�Ɋ��p���Ă���̂��낤���E�E�E�H
�@�����w���ł��Ȃ��݂̒��҂̋��n�V�����p�p�B
�u�ߑ����сv�ł͂Ȃ��A���E�ǂ��ŘA�����̂��Ƃ����u�A�Ύ��сv���猃���n��I�m�Ɍ������Ƃ������́B�@����ς�ߑ��������C�ɂȂ��Ă��܂����E�E�E�B
���@�A�����J���n�헪9�̒��_�@9�l�̑S�ăg�b�v�]�_�Ƃɂ����ق̋��n�ŐV���_
�u�S�ċ��n�E�ō��̉b�q�����W�A�Ǝ��̗��_��S���J�I�@
�Q�O���I�̔n����p�̂X�l�̃��[�_�[�������A�e�X�̐�啪��ɂ��ĐV���ȉ��߂��Ȃ��A���݂���я����\������郌�[�X�ɂ��āA���m�����I����B
�� �n���ɂ����������n ���@�̌��t�@���c ��� (��
�@�@�̂��狣�n�قǁA���̎�̃Z�I���[(�i���E��^)���L�x�ɂ���W���������Ȃ��̂ł́E�E�E�B
�@�@�Ⴆ�E�E�A�� �Җ]�̎őւ��ɑf���n����
�@�@�@�@�@�@�@�� �O��G1�D���n���I�[�v�����ʂɏo�Ă��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�� �O��1�Ԑl�C�S�s�n�͔���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �l�C���̓����n��_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �������̒ǂ����ݔn��_��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �_�[�r�[�n�̓_�[�r�[�n����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �Ă͖Ĕn�@�E�E�E�E �@�@�@�@�@�ȂǂȂ�
�@�@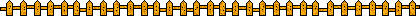
�@
�@���n�{�̐��E�ł��T���f�[�T�C�����X�͈�̃W�������ƂȂ����I
���T���f�[�T�C�����X��S�\�d�ܘA�ΎY��S���X�g �@�ʍ���
�@1990�N�̗A�����肩��2006�N�܂ŁA���{�̋��n��ς����Y��̊�����g�s�b�N�ŐU��Ԃ�uSS�X�|�[�c�v���I�[���J���[�Ŏ��^�B���̑��A�����̃f�[�^��|�[�g�ȂǂŁA�T���f�[�T�C�����X�̂��ׂĂ�ǂ݉���! �@
�@�t�W�L�Z�L���_���X�C���U�_�[�N���X�y�V�����E�B�[�N���A�O�l�X�^�L�I�����f�������_�����[���m���u���C���A
�����ăf�B�[�v���A�݂�ȃT���f�[�̎q���������I
|
| �����n |
�� |
�� |
|
�@
�@�c�O�Ȃ���A�����ɂ͊S�������A����Ƃ������{��ǂ�ł��܂���B���܂�̉��̐[���ƁA���ꂪ�����ɔn���Ɍ��т��̂����肩�ł͂Ȃ����߁A���܂�������̂܂܂ł��B
�悢���Ђ���������Ă��炢�������炢�ł��B
�@�@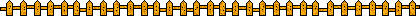
�����������n�������i�c�[�@���������j�A�X�L�[��
�������N���V�b�N���[�h�i�v�ėT���j���m���тȂǁA�����B�������߂ł���̂��ǂ����킩��܂���B
���߂�Ȃ����B
|
| �o�ڌn |
�� |
�� |
|
�@�o�ڂŏ�������Ƃ����̂͊m���Ə�������Ƃ������Ƃł��B�M�p�ɑ���f�[�^���c�O�Ȃ��猩������܂���ł����B
�@�@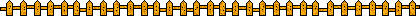
|
| �T�C���n |
�� |
�� |
|
�@���̑z���͕s�����A����Ŏg�p����ɂ͓�����܂��B�������������͔����ēǂ݂܂����B�������ߖ{�͓��ɂ���܂���B
�@�@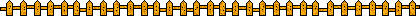 �@ �@
|
�i�q�`
�A�d���n |
���� |
�� |
|
�@
�@�ȑO�͂��̎�̘b�������\�D���Ńn�}���Ă�������������܂����B
�@���������́A���̔n���p�H�����Ƃɂ��āA�����ɔn��������悢�̂����킩��Ȃ��Ƃ������Ƃɐs���܂��B�킩�����Ǝ����Ŏv��������ł��A������m�F����p�͂���܂���A������Ȃ������܂łł��B
�|�M���邩�A�M���Ȃ����|�B
����Ӗ��ł́A�ЂƖ���������n�i�i�q�`�j�̐��E�����邱�Ƃ��o����Ƃ�����̂����E�E�B
�@�@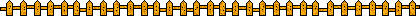
���i�q�`���ۗ��ɂ���n�����|�[�g�i�Љ������j���^�����o����
�s���̕Љ����̋��n�i�i�q�`���n�V�X�e���H�j���_�͔n���{�Ƃ���������������������ǂ�ł��邩�̂悤�ȓ�����̂������낳������܂��B�Љ����̖{�͑�������t
|
| �|�C���g�n |
������ |
���� |
|
�@
�@�������ނ���u�|�C���g�n�v�Ƃ́E�E�E�e�n�́u�����v�𐔒l�i�|�C���g�j�����ď����n���r��������B���̍ہA���l�����邽�߂ɕK�v�ȃf�[�^�͋��n�V���i�܂��̓X�|�[�c���j�̋��n���ɍڂ��Ă���n�������A���Ƃ͓d�삪����ΒN�ł��P���[�X�����`���\������ΐ��l���ł���Ƃ����̂������ƂȂ�܂��B
�@���́h�d�삪����A�P���[�X�����h�Ƃ����Ƃ��낪�ŋ߂̃X�s�[�h�w����R���s���[�^�[�w���ƈႤ�Ƃ���B
���n�̕K���@��҂ݏo�������ƍl����K���@��D���l�ԂȂ��x�͒��킵�����Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ہA�|�C���g�����o�����߂̃f�[�^�͔n���̓���Ƃ���ɗ����Ă��܂��B
�@��������Ă݂܂��傤�B
�@�@------------------------------------------------
�@�@�n��E���ʁE�o�������E�N���X�E�n���f�E�x�ݖ����E�O������
�@�@�O���l�C�E�����E�o�������E�S�R�[�i�[�ʉߏ��E�R��E�X��
�@�@�����~�Ȃǂ̗\�z�����B
�@�@------------------------------------------------
�@�����̃f�[�^�������ɐ��l�����A�g�ݍ��킹�邩���r�̌������ƂȂ�킯�ł��B
���āA�����̔n���{�ł����A���\�I�����܂��B��͂�P���̖{�Ƃ��Ĕ��\����킯�ł�����A���R��������ł��傤���A������x�̎��т��Ȃ���Ζ{�ɂȂǂȂ�Ȃ��̂ł��B
�@�匊�_���̔n���p�̏ꍇ�͐��\���[�X�̗�������Ώ\���ł��B�Ȃ����Ƃ����ƁA�����Ă��̐l�͔N�ԂɂP���[�X�ł��疜���Ȃǎ��Ȃ�����ł��B
�P�̂����łP�N�ɖ��������\�{��ꂽ��A����͂���ŃX�S�C���ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A���̂������N�Ԏ��x���v���X�ɏo����̂��ǂ����́A�܂������ʖ��ł�����ǁB
������f�[�^���P�̖@���ɉ����Đ��l�����A������g���ĉi���ɏ��������邱�ƁA���ꂪ�u���n�K���{�v���ɂ̃e�[�}�Ȃ̂ł��B�i���������Ȃ��āE�E�E�j��
�@�@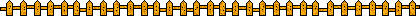
���y�{�莮�z�{�b�N�X�n���`�o�[�W�����K���@�i�{��p�l�jKK�x�X�g�u�b�N��
���{�͋��n�u�b�N�̖{����ƓƎ��Z�o�̔\�̓|�C���g����Ȃ�B�S���̃{�b�N�X�U�_�����B�X�S�C�̂́A�d�܃��[�X����Ȃ���X�X�D�P�O���_�܂ł̖�Q�N�W�����A���v���X�v�サ�Ă��邱�Ɓ�
��1000�~���P���~�ɂȂ��V�_�C�������h�n���p�i�H�R���v�j�A�[���Y�o����
��ŏ��̎����ő傫���ׂ���I�Ƃ�������匊�n���_�����B���ʂ̐l�����ʂɗ\�z������A�Ȃ��Ȃ������Ȃǎ��Ȃ��B����ł���x�͎���Ă݂����I�Ƃ������Ȃ��ɁB��
����������B
���������P�R�O�~���X�|�[�c�V���Ŕn�����v���ʂ������Ă��{(�����N��)���M�o�Ł�
��`����s���Ԃ��o����ߌ��ł���u��历�_���\�z�v�ŏ��āI�j�b�J���ł��X�|�j�`�ł��T���X�|�ł���m�ł��n�j�t
�@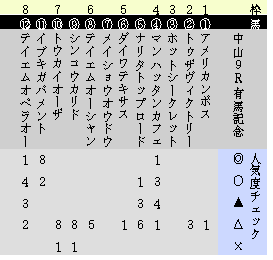 |
�����Ȃ݂Ɂu��历�_���\�z�v�Ƃ́H
�݂Ȃ�����������̒ʂ荶�L�̕\�́A���n��历�P�O���̗\�z����W�v�������̂ł��B�����Ă��̕\�́g�j�b�J���ł��X�|�j�`�ł��T���X�|�ł���m�ł��h�f�ڂ���Ă��܂��B
�@�܂肱�̐�历�l�C�x�`�F�b�N���g���ēƎ��\�z��g�ݗ��Ă悤�Ƃ����̂��A���̔n���{�̒��ƂȂ��Ă���܂��B
�ߋ��ɂ����̎�@�͑��݂����Ǝv���܂����A�ʂ����Ă��̎��͂́H
���Ȃ����̔n���{�����グ���̂��Ƃ����ƁA���͎������́u��历�l�C�x�`�F�b�N�v�ɂ͖ڂ�t���Ă��āA�g�����𗘗p���ĉ��Ƃ��I���n���ɂ�����Ȃ����낤���E�E�E�h�ƂЂ����ɍ������Ă�������ł���܂��B�������c�O�Ȃ���A����Ƃ���������v�������Ԃ��ƂȂ��A���̂܂ɂ��Y��Ă����Ƃ��ɁA���̔n���{�ɏo����Ă��܂����킯�ł��B |
�@���āA���́u��历�l�C�x�v���ǂ̂悤���|�C���g�����Ă���̂��́A�����ł͂����ď����܂��A���҂��u�\�z�Ɏ��Ԃ�������Ȃ����Ɓv����{�ɂ��Ă��邾�������āA�P���[�X�����Ŕ����ڂ��o���Ă��܂��܂��B�{���͂܂��Ƀ|�C���g�n�n���{�̊�{�ł���܂��B���������s�́A������g�������g���������p���邩�ɂ������Ă���h�Ƃ��Ă����܂��B
������n�����v���i�Ɠc�J�Y�I���j�A�[���Y�o�����@
�s�\�z�S�����Ȃ��u����n�v�̒�����A�����n�����Ԃ�o���B�K�v�ȃf�[�^�͑O�Q���̐��т݂̂ŁA�R���ŗ\�z�\�B�N������Ă����������ڂ��o��B�R�A���A�n�P�A�n�A�A���C�h�A�P���A���ׂĂ̔n���ɓO��Ή��B
�p�ӂ�����̂̓X�|�[�c�V���݂̂ŁA�P�_�P�O�O�~�ō��z�z����_�����A�匊�n�����H�p�B�t
�@�����ɂ܂��V���ȃ|�C���g�n�n���{���o�ꂵ�܂����B
�@�X�|�[�c�V���\�z���́u����n�v�݂̂ɏœ_���i�����Ƃ��낪�����B
�@��`����ɂ���g�N������Ă����������ڂ��o��h�Ƃ����Ƃ���́A�ǂ��炩�ƌ����g�N������Ă������|�C���g���o��h�Ƃ������i�����ɈႤ�j�B
�@�N������Ă������|�C���g���o��i����͓�����O���j�B������ׂČ��n������`���C�X�ł��B
���Ƃ��ǂ̂悤�ɔ��������܂��Ƀ|�C���g�ŁA�����ł����̂��A�R�A���ɂ��܂���̂��A�n�A�A���C�h�Ŕ����̂��́A���R�����瑤����B�i����Ɋւ���w�����������Ă���܂��B�j
�u���n�v�Ƃ����̂͂����T�����Ǝv���Ă������ȒP�Ɍ���������̂ł͂���܂���B�{���n�ƈ���ĂP���[�X�ɂR�`�W���͂��܂�����B�����ł��̃|�C���g�̏o�ԂƂ����킯�ł��B
�@�ʼn_�Ɂu���_���v�����邭�炢�Ȃ�A�܂��͂��̃|�C���g���w�W�Ƀ��[�X���ώ@����Ƃ����̂����\�����邩������܂���B
�@������̃|�C���g�̓��������ݎ������g�̔n���p�Ƃ��邽�߂ł��B
���|�C���g�n�n���p�i���ł������ł������j�̕K���@�́A�����ɂ��̃|�C���g�̓�����m�芈�p���邩�ɂ������Ă��܂�����B
���̈Ӗ��ł��̔n���{�͊��p�̂��b�オ����|�C���g�n�n���p���Ǝv���܂��B
�����҂̈Ɠc�J�Y�I���͂g�o�����J���B�u�P�������v
���z�[���y�[�W����������N�����Ă��������Ă���܂��B
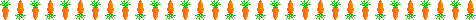
������������I���n�G�C�g�K�����_ (����������)���M�o�Ł�
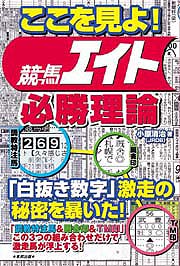 |
�@���n��历�w���n�G�C�g�x�̒������ŁA�����������ŋL����Ă��鐄���n�i�����������n�j�ɒ��Ⴕ�A�w���n�G�C�g�x�̊��p���@���Љ�����n�\�z�w�쏑�B �K�v�Ȃ̂́A�w���n�G�C�g�x����́A�u���������n�v�u�g���b�N�}���̈�v�u�X�Ɉ�v�����B
�@���n�I��Ɋ|���鎞�Ԃ́A�P���[�X�P��������n�j�B�g���b�N�}���ʂ̑_���ڂȂǗ\�z�ɗp����f�[�^�͂��ׂĂ�����Ă���̂ŁA�\�z���X���[�X�ɐi�߂���B
�֓��ŁE���ł̗����ɑΉ��B |
�@
�@�����n��历���g�p����[�\�z�@]�͌��\����Ă���悤�ł��B
���̒��ł��A���n�u�b�N�����n�G�C�g�̐l�C�������̂ł����A�v���Ԃ�ɃG�C�g���g�����\�z�@����L�{�B���҂̏������́A���̕��ʂ̔n���{�ӂɂ��Ă��܂��B
���n�G�C�g���D�҂́A��ǂ̉��l����!?
|
| �I�b�Y�n |
���� |
�� |
�@ |
�@
�@�I�b�Y�Ƃ����Ύ��̓��ɐ^����ɕ����Ԃ̂́A�^�����@�����ł���܂��傤���B
�ŋ߂ł����I�b�Y�E�J�C���m���n���̖@���v�i�A���A�h�l���j�������u���n�̓X�[�p�[�n���p�v�i�u�b�N�}���Ёj���Ȃǂ��o����Ă��܂��B���Ȃ�Â����炱�̕���Ŋ���Ă��܂��B���̃f�[�^�̖L�x���ƁA�k���ȕ��͂͑��̒ǐ��������ʁA�Ƃ���������������܂��B�������Ȃ���A�����k�����ɂ��Ă�����̂��ǂ������J�M�ƂȂ肻���ł��B
�@�܂��f�[�^�d���h�Ƃ͕ʂɁA�������M�����Ă���̂��A�ُ퓊�[���j��h�ł��傤�B
���łɉ��x���o�ꂵ�Ă����������H�R���v���̒���ɑ�\�������̂ł��B���̔n���p�A���͌��؋������ŁA�ߑO���Ɉ�U�I�b�Y�����o���Ă����K�v������̂ŁA����������Y��Ă��܂��ƌ�Ō��ł��Ȃ��Ƃ����킯�Ȃ̂ł��B
������������ُ̈퓊�[�Ƃ����̂͂��邾�낤�Ǝv���܂��B
�������̃��[�X����肷�邾���̃f�[�^���������c�O�Ȃ��玝�����킹�Ă͂��܂���B��x�`�������W�������Ƃ�����܂����A���܂�ɃI�b�Y�Ƃɂ�߂����ł����̂Łi���B���n�ɂ������悤�ȋǖʂ��m���ɂ���܂����E�E�A���̔�ł͂Ȃ��ł�����j���Ă��܂��܂����B
���I�b�Y�Ƃ͍ŏI�I�Ɏ������̗\�z����ҁE�~�]�Ȃǂ��ׂĂ��W�������ł��̂ŁA���̃I�b�Y�n�n���{�A���ꂩ����ڂ������܂���B
�@�@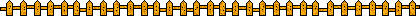 �@�@ �@�@
�I�b�Y�n�ɋ����̂�����́A��قǓo�ꂵ�Ă����������y�^�����@���z���̒�����ǂ�ł��悢�̂ŁA�����ɂȂ��Ă݂Ă͂������ł��傤���B
|
�X�s�[�h
�w�� |
������ |
�� |
�@ |
�@�X�O�N��O���A���n�u�[���˓��Ɠ����ɓ��p���������H�X�s�[�h�w������ю��v���_�B
���݂̈�ƂɂP��̃p�\�R�����ォ�炷��ƁA���̃X�s�[�h�n�͗���ׂ����Ă������_�ł͂���܂����A�����A����ɂǂ��Ղ�͂܂��Ă��܂������́A����͂�������ꓬ�̓��X�ł���܂����B
�p�\�R���͂����Ă��f�[�^�i���j�^�C���j�̓��͂͂������ꓪ�ꓪ����́B�������O�T���B�e���[�X�o���n�S���̃^�C�����o���낤�̂ɔ�₵�����Ԃ͂R�O�`�T�O�����炢�B���ꂩ��\�z�ɓ���킯�ł����A�Ƃɂ����e�n�̃^�C�����C�ɂȂ��Ă��傤���Ȃ��i������O���j�B�܂�A�O�T�����ς��Ă��������ő���n������A���郌�[�X�����߂���߂��ᑬ���^�C����@���o���Ă���z������B���āA�ǂ��������̂��Ƃ��炭�Y�݁A�����ł܂��S�O�`�U�O���B
�@���ǐF�X�Ȕ������������Ă݂܂����B
�P�D�Ƃɂ����P�Ԃ͂₢���v���������n�{�ŋ߂悢�^�C���ő������n�R�`�S��
�Q�D�O�R���ɍi��A���̒�����͂₢�^�C�����o�����n�A��ʏ��ɂS���`�T��
�R�D�O�R���ڂ���m���ɂ͂₭�Ȃ��Ă���n�i���q���オ���Ă��Ă���j�S�`�T���@�ȂǁE�E |
����������₵�����ԕ��A���Ԃ肪����A�g�w�͂���Ε����h�ŁA�^�C���ɑ��郂�`�x�[�V���������������邱�Ƃ��ł�����������܂���B
�������A��Ԃ͂��߂ɏЉ���g��{�n�h�\�z�Ǝ��x�̏�ł���قǍ����Ȃ��Ƃ������ʂɁA���R�Ǝ��̗\�z�̓X�s�[�h�n���痣��Ă������̂ł��B
���X�s�[�h�w���E���v���_�Ɋւ��ẮA�����Ŏ��������܂ł��Ȃ��A�l�X�Ȗ��_������Ă��܂��B�i�������A�f�[�^���͂Ɋւ��Ă͂i�q�`�|�u�`�m���̃T�[�r�X�⎩���v�Z�\�t�g�������o����Ă���̂Ōl�ŕ����J�͂͑������������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��j
����������b�g������܂��B
�E����܂ŃC���[�W�ł����c���ł��Ȃ������e�n�̋����i�����j���u�����v�ŕ\���A��r�����ł���B
�i�����Ƃ����Ă���n�́A�{���Ɂg�͂₢�h�̂��H�l�C�̂Ȃ��n�͂���ς�g�������h�̂��j
�E�l�C�̖ӓ_�ɂȂ��Ă���n�i���n�j�̔����A�����ď��X�ɒ��q�������Ă���i�^�C���ɂ����āj�n�̔����ɖ𗧂B
�~���ł��u�����n�����v�킯�ł͂Ȃ����Ƃ͊m���ł��傤���A���̖����ɑ��݂���v�f���l���ɓ���Ȃ��ƈӖ����Ȃ��Ƃ����b�������̒ʂ肾�Ǝv���܂��B���A�����Ă��̃X�s�[�h�w���n���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ȃ��ł��傤�B
�����̃X�s�[�h�n�́A�\�z���鑤�̐l�Ԃ��A�s�m���ȋ��n���[�X�Ƃ������E�ɁA�����i�X�s�[�h�w���j�Ƃ����m���Ȑ��E�����o�������Ƃ�����]���琶�ݏo���ꂽ���̂�����ł��B
�@�@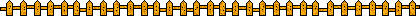
�����n�����ׂ��閧�̖@���i�ΐ� ���^�����j�x�X�g�u�b�N���s���s�N����1991.10�ł�����A���ꂩ������P�O�N�o���Ă��܂��܂����B�{�̃^�C�g�����炾�ƁA�i�q�`�A�d���n���Ǝv�킹���܂����A���^�����A���v���_�{�ł��B���҂̐ΐ쎁�̎��͍��ł݂͂Ȃ���悭�������ł��傤���A���ɐ����͂̂���_��W�J���Ă������ł���܂��B���킭�A�u���n�Ƃ́A�������n�����Ƃ������ƁB���̒P���Ȏ�����Y�ꂽ��A�n���͓�����Ȃ��B���n�͂����ƉȊw�I�Ȃ��̂ł���A�f�[�^�ɓ���Đ��_��ςݏd�˂���̂��v�@�ǂ��ł����A�v�킸���Ȃ��Ă��܂��܂��B���͂܂�����ɂ͂܂����킯�ł��ˁB
�ΐ쎁�͂��̌�������o�ł���Ă��܂��B���n��ʁE�Q�[�g�ʂƁA����ɂ��̗��_�ɖ����������Ă���������l�q�ł��t
�����c���X�s�[�h�w�� ���n�����l��I���ق̃^�C����͖@ �i���c �a�F���j�x�X�g�Z���[�Y��
�s���ɏo���̂��A�������c���ł��B�X�s�[�h�w���̌���œo��́A�ΐ쎮���v���_���x��邱�Ɩ�P�N�B
���̌�̓p�\�R���p�\�t�g���X�[�p�[�p�h�b�N�d�w�o�d�q�s
���c���X�s�[�h�w���v�Z�����n�f�[�^�x�[�X�\�t�g�F�����R�~���j�P�[�V�����Y���ȂǂŖ��N���c���X�s�[�h�w�����D�҂𑝂₵�Ă���͗l�ł��t
�������n��T���I�i�A���h�����[�E�x�C���[�j���^�����o�����܂������n���{���ۂ��Ȃ��Ƃ��낪�V�N�ł����B
���E�q���n�\�z�ɂ����āA�����^�C���w���n�ɂ͂܂邱�Ƃ́A�����A��x�ƂȂ��ł��傤�B�Q�l�ɂ��邱�Ƃ͂���H��������܂��r
|
| �R���s�w�� |
���� |
���� |
 |
�@�@���n�K���{�̐��E�ł́A�ߋ����猻�݂Ɏ���܂ŁA�l�X�ȁu�`�w���v�ƌĂ����̂����܂�Ă��܂����B
���̑��������ƂƂ��ɕ������Ă������ŁA���ݎw���̒��_�ɌN�Ղ���̂́A���̃y�[�W�ł��Ɨ��������ڂƂ��Ĉ����Ă���u�X�s�[�h�w���v�ł���܂��傤�i�����j�B
�u�n���v�O�T���̏�ɏ��������������i�X�s�[�h�w���j�܂��͗\�z�\�t�g�Ŕn���̉��ɋL���ꂽ�����߂Ȃ��珟���n�𐄗�����̂͂Ȃ��Ȃ��m�I�Q�[�����Ńn�}��₷���A�Ǝv���܂��B�X�s�[�h�w���Ɋւ��鎄�̍l���͏�ɏ����Ă���܂��̂ŏȗ����܂����A�ǂ���珟���n�\�z�ɂ����ăX�s�[�h�i�^�C���j�͍��ł͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ɐ��������悤�ł��B
�@�ł́A���ɑ����̔n��������x�����ꂻ�̎w����p���ĕK���@����������Ă�����̂͂Ƃ����u�`�w���v�ɂȂ�̂ł��傤���B
�u�W�J�w���v�ł��傤���A����Ƃ��u�r�c�w���v�u�Ĕn�w���v�u�n�͎w���v�u�����w���v�u�����n���w���v�u�l�C�w���v�ł��傤���B
������g�����h�Ƃ������߂����Ă��܂��܂����A�������Ă�������ɂ����đ����̔n���{�ŗ��p����M�p����Ă���w���͓����X�|�[�c���i�y�E���j�ɖ��T�f�ڂ���Ă���u�R���s�w���v���Ǝv���܂��B
�@�i�����R���s�w���ɂ��Ă͂�������Q�Ƃ��Ă��������B �E���g���I�j�b�J���X�|�[�c�E�R�� �j �E���g���I�j�b�J���X�|�[�c�E�R�� �j
�����u�R���s�w���v���x�[�X�ɍ��o���ꂽ�n���K���@�B
���̓X�s�[�h�w����肻�̗��j�͌Â���������܂���B�����X�|�[�c�Ɂu�R���s�w���v���o�ꂵ���̂��P�X�V�T�N���ƕ����܂����A�ŏ�?�ɂ��́u�R���s�w���v�����p�����n���{�͂W�V�N�ɏo�ł��ꂽ���n���̎����r�^�����߂�@(���F�Y��)�����Ƃ����b�ł�����A�W�O�N��ɂ͂����o�ꂵ�Ă����킯�ł��˥���B���͎c�O�Ȃ��炻�̒P�s�{�m��Ȃ������̂ł�������B���̌ケ�̃R���s�����p�����n���{�A�����̋��n�G���Ɏ��グ���b��ɂȂ����i�����w�������j�n���{���������o�ł���܂����B
�@�@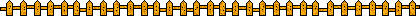
���V�����I�n�A�\�z�̐������_�@���K�g���`�b�v(����ҍL)KK�x�X�g�Z���[�Y��1994.5
���ѓc���X�[�p�[�R���s�n���p�@�n�C�p�[�i�r�Q�[�V����(�ѓc��v)��������1998.10
���R���s�d�l�P���������ŋ��̏o�ڗ��_(�o�ڗ\�z�{����y����)���^�����o����1998.12
�������R���s���S�U���u���C�h�n�������̖@���v(���� �Ђ��)�O�b���[��1999.10
���ѓc���X�[�p�[�R���s�n���p�@�n�C�p�[�i�r�Q�[�V�����Q�O�O�O(�ѓc��v)��������1999.10
�����n�E�����̐헪(����ҕF)���鏑�[��1999.11
���������P�R�O�~�ő�I�������X�|�[�c�K�����_(��� �N�i)���^�����o����2002.2
�������X�|�[�c�͉����̕K���@�������I(��� �N�i)���^�����o����2002.6
�ȂǂȂǂł��B
�������ɑ���R�����g�͏����܂���B�n���{�D���ȕ��Ȃ炱�̒��������ȏ�!?�͎�ɂƂ��ė����ǂ݂܂��͍w�����Ď��ۂɂ��̈З�??��̌����Ă��邾�낤�Ǝv������ł��B
�����A�������K�g���`�b�v�Ƀn�}��܂����B�܂��f�ڂ���Ă������сA���ɂV�J�ØA���v���X�B���ɋ����܂����B�i�K���@�Ȃ̂����瓖����O�̘b�łȂ��Ă͂����Ȃ��̂�����ǥ���j�@
���̃V�X�e���ɂ�蔃���ځA�������͌��肳��Ă���킯�Ȃ̂ŁA��ϓI�v�f�����荞�ޗv�f���Ȃ��A�֑�L���͑łĂȂ��͂��ł�����A�V�J�ØA���v���X�K���@�Ɏ����̂����킯�ł��ˁB
����������A���ɉ^���Ȃ��̂��A����Ƃ������̃o�C�I���Y���̂����Ȃ̂��A�����`�������W���n�߂���������߂�����З͔͂������A���ĂȂ�!�@�Ȃ���!!�@�Ȃ��Ȃ̂��[�A�Ƌ��т͂��܂���ł������A���N���炢�Łi�悭���������ł����H�j������߂܂����B
���͂��̃g���E�}�i��U�����ȁj�����ł����������āA �N������Ă����������ڂɂȂ�n���p�ɂ͂����H�H�H�}�[�N�����ĉ���Ă���̂ł��B �N������Ă����������ڂɂȂ�n���p�ɂ͂����H�H�H�}�[�N�����ĉ���Ă���̂ł��B
�@�@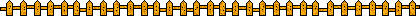
�@�P���[�X�P���[�X���R���s�w���i�ǂ�Ȏw���ł��\���܂��j��p���ăs���|�C���g�œI�������悤�Ƃ����͎̂���̋ƁB
���Ɂg�w���P�ʂX�O�̎��A�R�ʎw�����U�O�ȉ��ŁA�S�E�T�E�U�ʂ����������ť���h�ȂǂƎw�����ו��������̂������ʼn�����i�܂��͉�����Ғl�j���P�O�O���ȏ�ɂȂ����Ƃ��Ă��A���セ�̉�������ێ��ł���ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��A������肩�A����������͂P�O�O�������荞��ł��܂��ɈႢ�Ȃ��Ǝv���̂ł��B
���n�\�z�i���ɃR���s�w���Ȃǂ̎w���n�\�z�j�͌��ǂ͂��� �u�吔�̖@���v�Ƃ̐킢�Ȃ̂ł��B�w���ɂ���ă��[�X���ו������Ă��A���̃��[�X�I�𐔂�������Α�����قǁA�c�O�Ȃ��������͂V�O�`�X�O�����x�ɗ��������Ă��Ă��܂��B��������Q�O�O�Ƃ��R�O�O���Ƃ������ٓI�Ȑ�����@���o���Ă���̂͂����T���v���������Ȃ�����B���K�g���`�b�v�ɂ����ĂV�J�ØA���v���X���B���ł�����ɑ҂��Ă��錻���́A�V�J�ØA���}�C�i�X�ł���\�������������Ƃ������Ɓi���ۂ̓v���X�ƃ}�C�i�X���P�F�Q�̊����ł������Ƃ��Ă��j�B���̂��Ƃ��̎��͍l���Ă��Ȃ������̂ł��B�i�l�������͂Ȃ������j �u�吔�̖@���v�Ƃ̐킢�Ȃ̂ł��B�w���ɂ���ă��[�X���ו������Ă��A���̃��[�X�I�𐔂�������Α�����قǁA�c�O�Ȃ��������͂V�O�`�X�O�����x�ɗ��������Ă��Ă��܂��B��������Q�O�O�Ƃ��R�O�O���Ƃ������ٓI�Ȑ�����@���o���Ă���̂͂����T���v���������Ȃ�����B���K�g���`�b�v�ɂ����ĂV�J�ØA���v���X���B���ł�����ɑ҂��Ă��錻���́A�V�J�ØA���}�C�i�X�ł���\�������������Ƃ������Ɓi���ۂ̓v���X�ƃ}�C�i�X���P�F�Q�̊����ł������Ƃ��Ă��j�B���̂��Ƃ��̎��͍l���Ă��Ȃ������̂ł��B�i�l�������͂Ȃ������j
�����u�R���s�w���v�́g���h�̕����������Ă��Ă��܂��܂������A����������ɂ��܂��āu�R���s�w���v�����͓I�Ȃ̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă����̎w�����̂�����̂��₷���B���₷���ɂ���Ǝv���܂��B�P�q����P�Q�q�܂ł��P���ʂ̕Ћ��Ń`�F�b�N�\�Ȃ̂ł�����A����ȂɊy�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�������w���P�ʂ��X�O�Ȃ���I�b�Y��1�{��A�V�T�ȉ��Ȃ�3.0�ȏ�͂����낤�Ƃ����悻�̌��������A�ǂ̃��[�X���r�ꂻ���Ȃ̂��A���������܂肻���Ȃ̂����X�A�P���S�̂����[�X�X���̕��͂ɖ𗧂��܂��B
�@
�@�Ⴆ�G���U�x�X�����t���t�@�C�����[�V�����̎w���͂X�O�łP�ʁi���Ȃ݂Ɏw���ō��_�͂X�O�ł��j�ł������A�Q�ʔn�i�_�C�������h�r�R�[�j�Ƃ̎w�����͎��Ɂe�Q�T�f����܂����B����ɑ��āA�L�n�L�O�ł͎w�����ʂ͂P�ʂȂ�����A�w�����̂͂V�V�ŁA�Q�ʔn�i�V���{���N���X�G�X�j�̎w���͂V�U�Ƃ킸���ɂ��̍��́e�P�f��������܂���ł����B�܂�L�n�L�O�̕������͔����A�r��₷���X���ɂ��郌�[�X�������킯�ł��B�i�w���X�O�̔n����ɏ��Ƃ͌���Ȃ����Ƃ́A�P�{��̃I�b�Y�̔n���R�P�邱�Ƃ�����̂Ɠ������Ƃł��B�j
���֗̕����͑��̎w���̒ǐ��������Ȃ��ł͂Ȃ��ł��傤���B�i�l�b�g���������ł��܂����A�P�s�{����łȂ��A�l�b�g��Łu�R���s�w���v���g�����\�z�T�C�g���������ł�����j
�����ł����܂ł��Ȃ��A �u�|�C���g�n�v���l�A�w������ΓI�Ȃ��̂ł͂���܂���B���̂��Ƃ𗝉����A�ł��܂����ꂩ����u�R���s�w���v���g�������n�K���@�����ɏo�Ă��邱�Ƃ����҂��Ă���͎̂������ł͂Ȃ��ł��傤�B�������̒��̈�l�ƂȂ�ׂ����ݓ���Y�܂��Ă���Ƃ���ł���܂��B �u�|�C���g�n�v���l�A�w������ΓI�Ȃ��̂ł͂���܂���B���̂��Ƃ𗝉����A�ł��܂����ꂩ����u�R���s�w���v���g�������n�K���@�����ɏo�Ă��邱�Ƃ����҂��Ă���͎̂������ł͂Ȃ��ł��傤�B�������̒��̈�l�ƂȂ�ׂ����ݓ���Y�܂��Ă���Ƃ���ł���܂��B
����͗]�k�ł�������B
 �u�I�b�Y�n�v�Ŏ����g�I�b�Y�Ƃ͍ŏI�I�ɁA�������̗\�z����ҁE�~�]�Ȃǂ��ׂĂ��W�������h�ł���Ə����܂������A�I�b�Y�ɂ͂������n�̋����A�����A�����ė\�z�Ɛl�C�Ƃ����v�f���܂܂�Ă��܂��B���Ƃ�����́u�R���s�w���v�́A���̃I�b�Y���玄�����̊��ҁE�~�]�i�v�f�j�����������̂ƍl����悢�̂ł��B�������̊��ҁE�~�]�i�v�f�j�����f����Ă��Ȃ����A���I�b�Y�l�C�Ƃ͂��̏��ʂ��قȂ�܂����A�}�N���I����ɂ��ĂΈĊO�I�b�Y�n�\�z�Ƃ���قǑ傫�ȈႢ�͂Ȃ��̂�������Ȃ��A�Ǝv���Ă���܂��B �u�I�b�Y�n�v�Ŏ����g�I�b�Y�Ƃ͍ŏI�I�ɁA�������̗\�z����ҁE�~�]�Ȃǂ��ׂĂ��W�������h�ł���Ə����܂������A�I�b�Y�ɂ͂������n�̋����A�����A�����ė\�z�Ɛl�C�Ƃ����v�f���܂܂�Ă��܂��B���Ƃ�����́u�R���s�w���v�́A���̃I�b�Y���玄�����̊��ҁE�~�]�i�v�f�j�����������̂ƍl����悢�̂ł��B�������̊��ҁE�~�]�i�v�f�j�����f����Ă��Ȃ����A���I�b�Y�l�C�Ƃ͂��̏��ʂ��قȂ�܂����A�}�N���I����ɂ��ĂΈĊO�I�b�Y�n�\�z�Ƃ���قǑ傫�ȈႢ�͂Ȃ��̂�������Ȃ��A�Ǝv���Ă���܂��B
�n�̐�ΓI�\�͂��w�����i���C�e�B���O�j����Ȃ�t�@�C�����[�V�����͏�ɂX�O�O��ł���͂��ł����A���́u�R���s�w���v�����ΓI�]���i�����[�X�ɏo�鑼�n�Ƃ̐l�C�E���͂̌��ˍ����j�Ő����������o����Ă��܂��B�������I�b�Y�l�C�ɋ߂��Ƃ���ł���܂��B
| �@�o�r�D���ׂẮu�w���v�Ɋւ��ā@�i�O�R�D�P�O�^�S�j |
�@�����ł͓����X�|�[�c���i�y�E���j�ɖ��T�f�ڂ���Ă���u�R���s�w���v�Ɋւ��đz�����Ƃ������Ă݂܂������A���ǁA��Ԋ̐S�Ȃ��Ƃ́A�u�w���v���̂͂����������ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@�ǂ�ȂɁg��ԃo�b�g�h�������Ă����Ƃ��Ă��A��Ƀz�[���������łĂ�Ƃ͌���Ȃ��B�����������Ƃł��B
�@
�@�܂��A��Ԕ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�u�w���v���̂����o���i���ݏo���j��Ƃɖv�����A����i�w���j�����o���オ��i����ɓ���j�A�����オ��ɂȂ��Ă��܂��i�]�͂��c����Ă��Ȃ��j��Ԃł��B
�@�ǂ�Ȃɂ���낤���A�ŋ��̂o�b����g���悤���A�S���[�X�P�`�R����I����������悤�ȁu�w���v�Ȃǂł���͂��͂���܂���B
�@�����ŗl�X�ȁu�w���v��o�ꂳ���܂������A�������������������W���[�ȁu�w���v�ł���A�ǂ��i����j�Ƃ��Ďg�p���Ă����Ȃ��͂��ł��B
�@�����l����ƁA����Ȃ�E�E
�������ŁA���ȒP����ɓ�����̂�I�����悢�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
��́A����������Ɏg�����A���̓_�����ɐ��͂𒍂��A�W������I
�g�������̎w�����������̎w�����h�A���ꂾ���͔����������̂ł���܂��B
�i�u�u���b�N��!�n�������v�ɂ����ẮA�f�[�^�Ƃ��ď�L�u�R���s�w���v���O�R�N�S�����i�I�b�Y�l�C�ƕ��p���邩�����Łj�̗p���Ă���܂����A������f�[�^����̂��₷���ƁA���̉��i�I�Ȃ����ɂ�锻�f�ł���܂��i�� �I�b�Y�l�C�͖����^�_�œ���ł��܂����A�����Ƃ�������Ȗ�������܂��j�B�������A�ǂ̎w���f�[�^�ɂ����Ă����Ă͂܂�܂����A���̃f�[�^�̐M�����A�p�������͌����Ȃ���Ύg���܂���B���R���̌��͂����Ȃ��Ă���A���̌��ʁA�̗p�����Ƃ������Ƃł��B
�ȏ�B
|
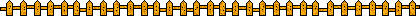 |
|
���Q�O�O�T�N�܂��V�����w���n�n���{����������܂����B
�@���̖����h�j�w��
| �����X�|�uIK�w���v�p�[�t�F�N�g�K�C�h�@�i�v�ā@�T���j�@���鏑�[�� |
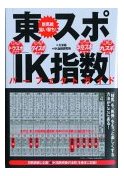 |
�@���X�|�́u�h�j�w���v���g�����n���p���{�ɂȂ�܂����B
���҂́A���́u�����N���V�b�N���[�h�v�̋v�ėT���B
�����{�̒��҂��Ȃ��I�H�@�Ȃ�قǂ���́A�A�u�����N���V�b�N���[�h�v�̑啝���j���[�A���Ȃ̂ł����B
�@���X�|�E��X�|�E�����X�|�E��X�|�̋��n�ʂŐl�C���Ă���Q�Δn�̔\�͎w���E�u�h�j�v�w���̎Z�o���@�Ɛ��������p�@���w��I�@�V�n�E��������ŐϋɓI�ɍ��z����_���n���p�����J�E����v�Z��������͈�Ȃ��I�@
|
|
���C�e�B���O
 |
���� |
������ |
 |
�@���݁A�����R���s�w���ɑR�ł���w���Ƃ��āA�l�C�E���͂����˔����Ă�����̂͂ƕ������A��͂苣�n�u�b�N�����C�e�B���O(=�i�t��)�f�[�^�͊O���܂���B
�u�w���v�ƌĂ����̂���L�́y�R���s�w���z���ł��������Ƃ���A���������荡��������Ă������̂Ǝv���܂��B�������A�f�[�^�Ƃ������̂͌p���ƐM������B
�f�[�^�����s������������肵�Ă��Ȃ���A�n�������ɂ͎g���܂���B
���̈Ӗ��ŁA�����X�|�[�c�V���ЁA���P�C�o�u�b�N�Ƃ�����̂��쐬���Ă���f�[�^�ɂ́A���S��������̂ł��B
���C�e�B���O�ɂ͂����ЂƂ��|���Ђ���������u���n�t�H�[�����v�쐬�̂��̂�����܂��B����������p���Ă���������邱�Ƃł��傤�B�������A���y�x(=�n���{�ł�)�Ƃ����_�ł́A���n�u�b�N�̃��C�e�B���O�ɂ͋y�Ȃ��Ƃ��������ł��B�Ǝ��̃��[�g������̂Ŗ��Ȃ��̂ł��傤�B
���ɂ��A�l���쐬����Ǝ��̃��C�e�B���O�f�[�^������܂��B
�w�����̂͂ǂ�����������g���郌�x���ɂ͂���Ǝv���܂����A���ǍŌ�́A���̃f�[�^��������肵�Ă������Ƃ��ł��邩�ǂ����E�E�E�B
���͂����Ȃ̂ł��B
�f�[�^�͌p�����Ă����͂ɂȂ��B
�r���œ���ł��Ȃ��Ȃ�悤�ȉ\���̂���f�[�^�Ȃ�A�͂��߂���g���悤�����X�N�͔����Ȃ���Ȃ�܂���B������O�̘b�ł��B
���́A�f�[�^�Ȃǂ�����x���y���Ă�����̂Ȃ牽�ł��\��Ȃ��̂ł��B�̐S�Ȃ̂́A������ǂ��g�����A�ǂ����������I
�f�[�^���̂̍쐬�Ɏ��Ԃ��₵�Ă������A�n���̏��҂ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝ��͍l���Ă��܂��B
�j�b�J���R���s�w���ɂ��邩�A���n�u�b�N�̃��C�e�B���O���g�����A����Ƃ��h�j�w��(���X�|��)���Q�l�ɂ��邩�́A�e���̍D�������Ō��߂Ă����Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
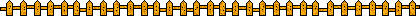
�@���C�e�B���O�֘A�̔n���{
| �����n�u�b�N�̂�����������Ζׂ���܂��I��� �N�i�� �@���^�����o�� |
 |
�@���n�u�b�N�����C�e�B���O�ƒP���\�z�I�b�Y���g���ΊȒP�A�v�Z�s�v�ŃA�b�Ƃ����܂ɓ����ꔭ�B
��历�w���n�u�b�N�x�̏o�n�\�������g���āA���ߋ��̗��ɍڂ�n(��n)��T���o�����@�ƁA���̎������Љ�B
|
| �����n�u�b�N���C�e�B���O�d�l�r�i�s�����͗��_�@�o�� ���� |
 |
�u�����n�v�̔\�͂Ƃ̓T���u���b�h�P�̂̔\�͂ł͂Ȃ��B
�n�ƋR��ƒ����t���O�ʈ�̂ƂȂ��Č�������̂��B
�w���n�u�b�N�x�����C�e�B���O�ƁA�R��E�����t�̘A�Η����g�����A�����n�̑����͂̊���o�������Љ��B |
|
|
����
���B�n |
������ |
������ |
|
�@�u�u���b�N���n�����B�p�v�ނ킯����ƁA���̓������B�n�ɓ���܂��B
�ł�����A�{���Ȃ�܂��͂��߂ɁA��������U�߂Ȃ��Ă͂����Ȃ������̂�������܂���ˁB
���Ƃ����铊�����n�Ƃ̏o��́A����(2001�j����V�N�O�ɂ����̂ڂ�܂��B
���̔n���{�̃^�C�g���́��g��w�����������H����h���n���_�i���쏃���j�j�j�x�X�g�Z���[�Y���ł����B
�����X�ɍs���Ă����܂肨�ڂɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂������A�����͑�w�������Ƃ������ЁH�ɑ���Ȋ��҂����������Ƃ��o���Ă��܂��B
�@���̏������̗��_�ʼn���I�������̂́i���ɂƂ��āj�A�e���[�X�̓��������ϓ��������ł͂Ȃ��A�I�b�Y�����ɁA��������ɓ��Ă͂߂Ă����A�����ƃv���X�ɂ����Ă�����A�Ƃ������̂ł����B
�܂�A�ǂ̔n�������Ƃ������Ƃ��A���q����Ζׂ��邩�ɏd�_���u����Ă����킯�ł��B
����܂ł̔n���{�́A�قƂ�ǂ��ϓ��������A���������A�u���߁v�u���߁v�ɔ����Ƃ����������x�ŁA�������i�q�����j�Ɋւ��ẮA�g�݂Ȃ��܂̂����R�Ɂh�Ƃ������Ƃł�������A�Ȃ�قǂ��������q����������̂��Ɗ��S�������̂ł��B
�������A�q�������Z�o���邻�̌�����������Â炩�������ƁA�̐S�̔n���̑I�o�̎d���ɂ���Ƃ�������p���Ȃ��������ƂȂǂŎ��H����܂łɂ͂�����܂���ł������B
�����������Ă��邤���Ɂi�X�s�[�h�w���n�ɂ͐��̏�ł͋y�Ȃ����̂́j�A���X�Ɠ������B�n�ɕ��ނ���邾�낤�n���{�������Ă��āA����قNJS�̂Ȃ������s�����̎��̓|�C���g�n�ƃX�s�[�h�w���n�ɂ͂܂��Ă����t���ɂƂ��Ă������ł��Ȃ����݂ɂȂ��Ă������Ƃ����킯�ł��B
�����̎��I��\�n���{�����ꂩ�炲�Љ�����܂��B
�@�@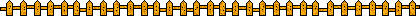
���n����BOOKS�Q�u���n���e�N�u���v�i���[�T��j���W�I�������
����͌��\���ꂽ�{�ł����A�����̓����n���{�Ƃ��Ă͂悭�ł��Ă���Ǝv���܂��B���������������̂����ł����A����������ǂ����͓���Ƃ���B���̗��R�i�킯�j�������ŏ����Ă悢���̂Ȃ̂��ǂ����E�E�E�B���������ł�������@�_�����B
��{�́A�u�g�A�R�_���{�����v�ł��B�ȏ�B
���P�O�O�~�ʂł͂��߂�����̍��e�N�V���_�i����m�u�j���烁�f�B�A��
�@���߂ď��X�Ō����Ƃ��́A���n�̖{�Ȃ̂��ǂ����킩��Â炩�����̂ł����A���ƂȂ��Ă͑����̕�����x�͎�Ɏ�������Ƃ����邾�낤�x�X�g�Z���[�{�B���̖{���������n�{�Ƃ����W���������m�������ƌ����Ă������߂��ł͂Ȃ��ł��傤�B
���̒��ŏЉ��Ă����w�n�@�̕������x�͑O�q�����u��w�����������H����h���n���_�v�̓������Z�o�@������ɃV�F�C�v�A�b�v�������X�O�����̂ł����B
���҂��犮���҂܂Ōv�S���o�ł���Ă��܂��B�n���̑I�o�̎d�����A���̒���_�͉ߋ��ɂȂ����̂ł����B
���S�Ȃ�n���{�ȂǂȂ��̂ł��傤���A���Ƃ́A�����Ɏ���Ŏg����悤�ɐi�������Ă������A
������l����͎̂������̑��ɂ���̂��Ǝv���܂��B
�����n���T�C�h�r�W�l�X�ɕς����헪�o���_�i�ӎ}�j�N��401������j���^�����o����
�@�X�W�N�ɏo�ł��ꂽ�{�ł����A������n���i�����ځj�I�o�ɗ\�z��K�v�Ƃ��Ȃ��A�S���V�����헪���������Ă��܂����B
�S�n�����w������Ƃ����V���z�ł��B����ł����Ɏ��x���v���X�ɓ����Ă����̂��̃m�E�n�E�͖{����ǂ�ł���������������܂��A������V�����������n�̕��@�_�Ƃ��Ă���ɐi�������Ă����ė~�������̂ł��B
���������B�n�Ƃ����W�������́A���n���u�n�̋����A�����v���画�f�������n��\�z����Ƃ������y���݂����킦�Ȃ����̂�������܂���B�������������܂Œʂ�́g�\�z���y���ނƂ������������h��������Ȃ�������Ȃ��킯�ł͂���܂���A�v���X���x�ɒ��킵�����Ƃ������Ȃ��x�͂��̐��E���̂����Ă݂Ă��悢�̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂��B
������̍ۂ́A���R�U�T���Ԃŏ��������u�u���b�N���n�����B�p�v�������Y��Ȃ��B�i�O�O;�j
�@�������n�֘A�̔n���{
| ���n�������R�O���~���k�� �@�n�[�g�s�A���n���{�� |  | �@�������n�̃m�E�n�E���A��b�`���ʼn���B
�Ȃ��Ȃ��n����������Ȃ��Ƃ����l����A���n�ɂ��܂�ڂ����Ȃ��l�A�n����I�Ԃ̂��ʓ|�Ȑl�܂ŁA���̂P���ʼn҂��̔錍���킩��I
����L�́u�P�O�O�~�ʂł͂��߂�`�v�V���[�Y�̍ŐV��
�܂��P���������Ă��Ȃ����ɂƂ��ẮA�ǂ����发�ƂȂ邾�낤�B
|
|
| �o�[�W�����W |
������ |
�� |
|
���o�[�W�����W�i�����r�꒘�j�j�j�x�X�g�Z���[�Y���P�X�X�Q�N�T�����s
�@���̔n���{�Ɋւ��ẮA�P�Ƃ̍��ڂƂ��Ď��グ�����Ǝv���܂��B
�Ȃ����H�@����́A���̖{�����̔n���{�T���S�ɉ���������ɑ��Ȃ�܂���B�܂莄�̋��n�l���ɂ����āA���́q�o�[�W�����W�r�����ɁA�O���E����ƕ����邱�Ƃ��o����Ƃ��������邩������Ȃ��̂ł��B
�����o�ł���Ă���X�N�ȏオ�����Ă��܂��܂����B�������̂ł��E�E�B
�@
�����A�X�s�[�h�n�ɖڊo�ߎn�߂����������̂ł����A�n���{�Ɋւ��ẮA�f�P���[�X���߂Â��Ɖ��C�Ȃ��n���{�R�[�i�[��`���Ă݂�Ƃ��������x�̊S��������܂���ł����B����Ȏ����R�o������̂����́q�o�[�W�����W�r�������̂ł��B
�@�n���K���@�̐V���_�|�o�[�W�����W�|�ƍ��܂ꂽ���̕\���ɂ́A�C���o�b�N�ɂ����ꓪ�̃T���u���b�g���ʂ��Ă��邾���ł��B
����܂ł̔n���{�̂悤�Ɉ����ۂ��g�h��ȍL���E��`�h�͂Ȃ��B
�����낤�A����́H�H���̖{���v�킸��Ɏ�������̓��̒��͏��X�������Ă��܂����B
�X�Q�N�����Ƃ����A�~�z�m�u���{�����_�[�r�[���������N�Ƃ����Ύv���o���Ă���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�|���n�u�[��������オ���Ă���Ƃ��ł��|
���́q�o�[�W�����W�r�A�������̕������������邩�Ǝv���܂����A�ŋ߂ł͂ǂ̏��X�ɍs���Ă����ڂɂ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�m���Ƀf�[�^�͌Â������Ȃ��Ă��܂��܂������A���ǂݕԂ��Ă݂Ă��A���̔��z���甃���ڂ̏o�����E�������܂ŁA���݂ł��\���ʗp����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�ȒP�ɂ��́q�o�[�W�����W�r���������ƁA��L�ɂ����u�|�C���g�n�v���u�������B�n�v���~�b�N�X���ꂽ���́A�ƍl���Ă���������悢��������܂���B
�@�|�C���g�Ɏg�p����͎̂��̂P�T���ڂŁA����ɍו�������Ă��܂��B
| ���� |
�����K�� |
�O������ |
�O�X������ |
���j�^�C��
�i�オ��^�C���j |
���� |
�R�[�X
�i�n�ꍷ�j |
�W�J |
| �n���� |
�R�� |
�R��Ƃ̑��� |
�����t |
| ���[�e�[�V���� |
���� |
�R�����g |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���|�C���g�n�Ƃ�����\��������قǂ̍��ڂł��B�j
�@��������Ƃɓ����o���������ڂ��g���������̂ł͂Ȃ��h���̔����ڂ��ǂ̂悤�ȃ��Y���ŏo�����Ă���̂��������Ă����Ƃ������z���A�����Ƃ��Ă͎a�V�ł������납�����킯�ł��B
�t�ɔ����ڂ̏o�������A���X���G�����āi�v�������������X�T���Ȃ�����ł��j�����Ŏ��H����ɂ͖���������܂����B�������A�Ȃ�Ƃ������ƊȒP�Ƀ|�C���g���o���Ȃ����Ƃ����ӗ~���A���̌�̎��̔n���i�K���@�j�����ɖ𗧂����̂��Ǝv���܂��B
���̌�A�q�o�[�W�����W�r�́s�o�[�W�����X�t�Ƃ��Ă���ɐi�������p���I���Ă���܂������A�i���������āA�l�Ŕ����ڂ��o���̂͂܂��܂�����ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�����s�o�[�W�����X�t�|�e���Əオ��̓����}���狁�߂�v�V�I�^�C���]����|�i�����r�꒘�j�j�j�x�X�g�Z���[�Y��
���ŋ߂̋��n�\�z�̒��ɂ́A�u�ߋ��\���N�E�ߋ��������[�X�̌��̌��ʁv�Ƃ��������t���×����Ă��܂����A���ۂ����M���邾���̍����Ȃ�f�[�^�Ȃ肪�f�ڂ���Ă��Ȃ��ꍇ�������Ȃ��Ă��܂��B�������Ɣ閧�Ƃ͂����A�P�ł��悢���牽������̍����i�f�[�^�I�؋��j����ė~�������̂ł��B
�����̖{�̖c��ȃf�[�^�ƌ��؉ߒ��̘J�́i�����Ƃ��Ắj�Ɍh�ӂ�\���āA�P�Ƃ̍��Ƃ��Ă��́q�o�[�W�����W�r�����グ������ł��B
�@
���E�Ȃ����́q�o�[�W�����W�r�͏�L�̃I�����C���V���b�v�y�����P�z�Ō������Ă�����܂���ł������A�������������@�ɂ́i���j�Ȃ���o�^����Ă��܂����B�ihttp://www.amazon.co.jp�j
|
| �@�u�R�A�P�v�n���{ |
|
|
|
�@�Q�O�O�S�N�P�O���R�����|�H�E�n���{�̋G�߂ł�Part�Q���甲���E�E�E
�@�����悢��H�̂f�T�V�[�Y�������ł��B�Ƃ������Ƃ́A���X�̕Ћ��łЂ�����Ƌ����\���Ă���n���{�R�[�i�[���ɂ킩�Ɋ��C�Â��A���R�A�N�Q��K���V���o�Ń��b�V�����n�܂��Ă���͂��B����͖{������ɍs���˂Ȃ�܂��E�E�E�I
�@�Ƃ����o�����ŏ����n�߂��O����u�H�E�n���{�̋G�߂ł��v�B�������̂ł��ꂩ��Q�N���o���Ă��܂��܂����B
�@�ߋ��̃R���������J���Ă��Ȃ���A���݂ł����̂܂g����o�����Ȃ킯�ł����A���ہA�{���ɍs���ƂQ�N�O�Ƃ͖��炩�ɗl�����ω����Ă���̂�������܂��B
�@�ǂ��ω����Ă���̂��Ƃ����ƁA�܂��n���{�̔����ʐς̌����E�k�����������Ƃ������ƁB�p�`���R�֘A�̖{�͔����Ƃ����������Ȃ̂ł����E�E�E�A����͎����悭�s�����X�Ɍ��������ƂȂ̂ł��傤���H�S�`�T�X�܂��܂���Ă����������������Ă���̂ł����A�ǂ��Ȃ̂ł��傤���B
�@�i�C�͏�����Ɛ��{�͂�������ǁA����ς���ۂ́u�n���{�ʐς̌�������y��팸�̏��������v�Ȃ�ĘA�z�������Ȃ�悤�ȏł͂Ȃ��̂ł��傤���B
������A�g�n���{�����Ă�������Ȃ�����N������Ȃ��Ȃ��ďk������Ă��܂��̂��h�A�Ȃ�Đ����������Ă�����E�E�E�B�ǂ���ɂ���A�n���{�̐��E�͌������ɗ�������Ă���̂ł���܂��B
�@�O��̃R�����ł͂��傤�ǁu�R�A���E�n�P�v�n�������������Ƃ����āA�n���{������ɂ��킹���^�C�g�������������킯�ł����A�����Ȃ�Ɠ��R���N���R�A�P�֘A�{�Ƃ������ƂɂȂ�܂���ȁB
�������ɁA�ȑO�قǂ̐����͂���܂��A����ł��������ɂ���܂��A�R�A�P�I
�@�ŋ߂̌X���Ƃ��āA�Ƃ����������Q�`�R�N�O����̌X���Ƃ��āA�u�f�[�^�{�v�������Ă��Ă��܂��ˁB
�@�i�q�`������ł����Ƃ������炢���푽�l�ȃf�[�^����X�ɒ��Ă����悤�ɂȂ����͍̂��Ɏn�܂������Ƃł͂���܂��A������������A���͂ł�������u���[�h�o���h�̕��y�ɂ���Đ����Ă����Ƃ������Ƃł��傤�B
�����n��ʁ����R�[�X�ʁ������[�X�����ʁ��������ʁ��ȂǂȂǁB
�@
�@���ĂȂ�l�����Ȃ������قǏڍׂɒ��ׂ��A���̎��̏����E�A�Η��Ȃǂ�g�����Ȃ���A���Ȃ��玫�T�݂����ɂȂ��Ă�����̂����邭�炢�ł��B
�@�f�[�^�͖L�x��������������ς��������ł����������ݏo�������ł��B
�@
�@�������A���ɂƂ��Ă��̎�̖{�ɂ͉��̖��͂������Ȃ��Ƃ����̂������ȂƂ���B
���͂��̃f�[�^�E�������g���Ă����Ɂu�����n�v�u�I���n���v����ɂ��邱�Ƃ��ł���̂��ɂ���܂��B
�@�����āA���́u�������v�̕������A�C�f�B�A���n���{�̌������ł���Ǝ��͎v���Ă���̂ŁA�P�Ȃ鐔���̗���A�f�[�^�̐��ꗬ���ɂ������������Ă��܂��̂ł��B
�@�܂��Ȃ��ɂ͂�������p���ēI���n������ɂ��Ă���l������̂ł��傤����A����͎��l�̈ӌ��ł͂���܂�����ǁB
�@���߂ɏ������u�n���{�̔����ʐς̌����E�k���v�ƒP�Ȃ鐔���i�f�[�^�j�{�̑����ɉ�������̈��ʊW�������Ă���͎̂������ł��傤���B
�@�ŋߎ����n���{��Ȃ��Ȃ�܂����B����������Ȃ��Ȃ����킯�ł͂���܂���B
���g�́g�n���̔������h���m������Ă����Ƃ������Ƃ�����܂��B
��������Ԃ̗��R�����͂���n���p�i�ׂ��肻���Ȋ��҂��������Ă����Ƃ����Ӗ��j�������Ă����Ƃ������ɂ���̂ł��B
�@�͂����肢�����R�A�P�B���Ă�̂͌������A��ؓ�ł͂����Ȃ��n���ł�����A��L�n���{�̐���͔@����!?�B
�@�E�E�E����
�@���Q�O�O�T�N�T���܂łɏo�ł��ꂽ�R�A�P�n���{�̈ꕔ
�E�i�q�`�A�d���n�̕Љ������������Q���ڂ����s�B���ς�炸�̓��e�����A�P���ڂł͂i�q�`�ɂ��Ă��ꂽ�̂��A����Ƃ����g�A�[�������Ȃ������̂��낤���H
�E�H�R�����n���{������ނ���ƌ��������Ȃ���A����ς�R�A�P�{�ɎQ�팈�s�I�I
�E�B�ꋻ�����������͕̂�鎁�̃V�X�e�����B
�@�c�O�Ȃ���A�a�V�ȃA�C�f�B�A�͂Ȃ�������ǁE�E�E�A�݂Ȃ���͂������ł����ł��傤���B
�@�i�Q�O�O�T�D�U�^�T�@�L�j
|